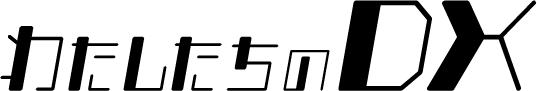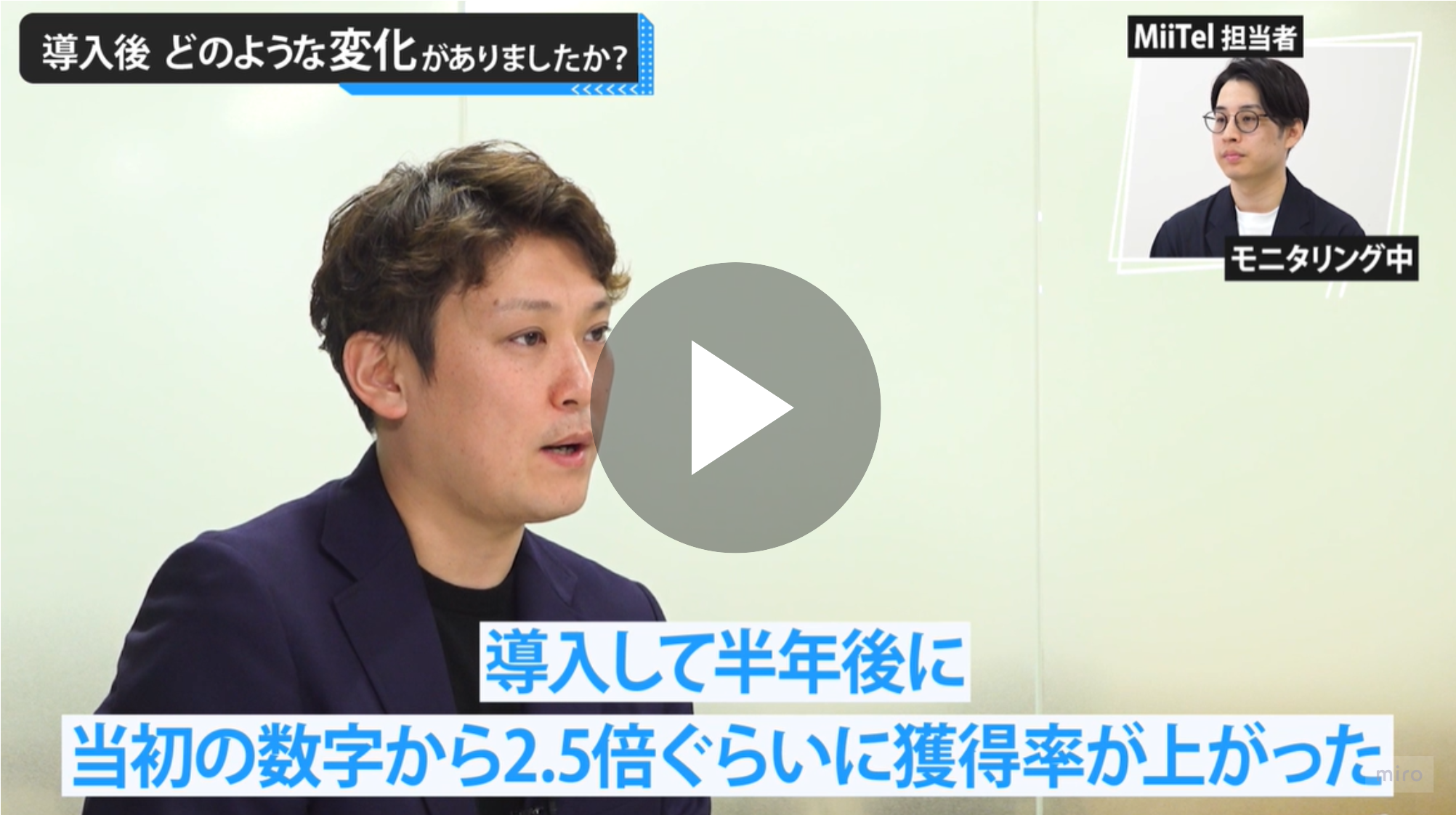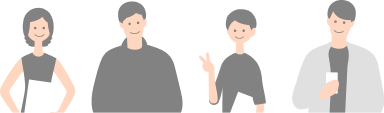ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、複数の設問が書かれたチェックシートを用いて、個人のストレスの度合いや要因について可視化する検査のことです。2015年の労働安全衛生法改正により、労働者が50名以上の事業所では、年に一度ストレスチェックの実施義務が課されています。
ストレスチェック制度は、労働者本人のストレス状態を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防の強化を目的に制定されました。また、ストレスチェックで得られた結果を分析し、労働者がより快適な環境下で働けるよう労働環境の改善に役立てることも期待されています。
参考:2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります|厚生労働省
ストレスチェックの対象者
50名以上の従業員を有する企業においては、パートタイム労働者や派遣先の労働者も含むすべての労働者が対象です。ただし、契約期間が1年未満の労働者や、所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者を除きます。
なお、従業員数50名未満の事業者もできるだけ実施することが望ましいとされていますが、実施における負担を考慮し、当分の間は努力義務とされています。

ストレスチェック制度の実施手順
ここからは厚生労働省のマニュアルにもとづいて、ストレスチェック制度の進め方を紹介します。
参考:ストレスチェック制度導入マニュアル|厚生労働省
導入準備
まずは社内でストレスチェックを実施する方針であることを示し、実施方法やルールなどを策定します。いつ、誰が、実施するのかなどのおおまかな方針を決めたうえで、質問票の項目や集団分析の方法、結果データの保存先や管理者の選定などを話し合います。
決定事項は社内規定として明文化し、社内全体に周知しましょう。
ストレスチェックの実施
ストレスチェックでは質問票を配布し、従業員に記入してもらいます。書類を回収する際には、プライバシー保護の観点から、必ず医師または補助役である実施事務従事者が行わなければなりません。
また、ITツールを利用したオンラインによるストレスチェックの実施も認められています。
結果の通知と面接指導の実施
医師などのストレスチェック実施者が質問票を確認し、ストレスの程度を判断します。結果は企業に通知されないため、「医師による面接指導が必要」と通知された従業員は、通知から一月以内に自ら面接指導を申し出る必要があります。また申し出があった場合、企業は申し出から一月以内に面接指導の機会を提供しなければなりません。
結果の保存と労働環境改善
事業者は、面接指導後一月以内に医師から意見の聴き取りを行います。就業上の措置の必要性や内容について検討し、労働時間の短縮などの措置をとりましょう。また、面接指導の結果については、事業所で5年間保存しなければなりません。
ストレスチェックの結果は医師などの実施者によって保存されます。鍵のかかるキャビネットやサーバなど、第三者に閲覧されない環境が構築できる場合は企業側で保管することも認められています。
ストレスチェック実施時のポイント
ストレスチェックは一定の条件下で事業者に実施が義務付けられています。しかし、ストレスチェックや医師面接を受けるか、ストレスチェックの結果を企業に提供するかどうかは、従業員の判断に委ねられているため注意が必要です。
ここからは従業員に能動的にストレスチェックを受けてもらうため、また企業側の負担を軽減するためのポイントについて解説します。
プライバシーの保護を徹底する
ストレスチェックの結果や面談指導の内容は個人情報にあたり、実施者ら情報管理を行う者に対して守秘義務が課されています。事業者がストレスチェック制度に関する従業員の情報を不正に取り扱うことのないよう、調査票や面談履歴などの書類・データの管理を徹底しましょう。メンタルヘルス推進担当や衛生委員に対して情報セキュリティ研修を実施するのもおすすめです。
集団分析の結果をもとに環境改善へ活かす
ストレスチェックのデータをもとにした集団分析は、法律では努力義務とされており、実施しなくても企業に罰則はありません。しかし、ストレスチェックで集めた個々のデータを分析すると、部署ごとのストレス傾向や、高ストレス者の多いチームなどがわかります。職場の環境改善につながるデータが得られるため、可能であれば集団分析を行うとよいでしょう。
自社に適した項目数を採用する
ストレスチェックに用いられる調査票に決まった形式はなく、各企業が自社に適した内容で用意しなくてはなりません。一から作成するのが難しい場合は、厚生労働省が出している簡易調査票を活用するのもよいです。しかし、23項目・57項目・80項目の3種類用意されており、どの項目数のものを採用すればよいか迷う担当者も多いでしょう。これらの特徴と違いは次のとおりです。自社に適した項目数を採用しましょう。
- ■23項目版
- 57項目の簡略版。ストレスチェックに必要な3つの領域は満たしているため、極力負担なくストレスチェックを実施したい企業に適している。
- ■57項目版
- 個人のストレス状況が5分ほどで簡単に把握できるため、多くの企業で採用されている。57項目をベースに、必要な設問を追加するのが望ましい。
- ■80項目版
- 57項目版に加えて、モチベーションやハラスメントなどの設問が含まれている。職場の環境改善につながるデータが得られるとして、近年企業から注目されている。
参考:職業性ストレス簡易調査票(簡略版23項目)|発行元
参考:職業性ストレス簡易調査票(57 項目)|厚生労働省
参考:職業性ストレス簡易調査票(80 項目版)|厚生労働省
外部委託やサービスの導入も検討する
主に産業医がストレスチェックの企画・評価を実施しますが、実施事務従事者として、社内の衛生管理者や事務職員などが医師らの補助をします。実施事務従事者は、調査票の配布や回収のほか、結果通知や面接指導の窓口となり、従業員数が多いほど業務が煩雑となりがちです。またある程度の専門知識が必要となるため、業務の属人化も懸念されます。
そこで、ストレスチェックを外部委託するのも一つの手です。セキュリティ管理が厳重な業者であれば、プライバシーの観点からも安心といえます。さらに、自社で実施するよりもコストを削減できる場合もあります。
外部の事業者に委託する場合は以下の点に留意して適切なサービス業者を見つけましょう。
- ●予算やサービス内容に見合った料金体系か
- ●設問数や受検方法などの設定に柔軟性があるか
- ●集団分析が充実しているか
- ●高ストレス者に対するフォロー体制が用意されているか
- ●プライバシーマークやISMSを取得しているか
ストレスチェックの外部委託を検討したい方は、以下の記事でおすすめのサービスを紹介しているため、参考にしてください。
関連記事

ストレスチェックを効果的に実施し健康経営を実現しよう
従業員を50名以上有する企業ではストレスチェックが義務化されているため、従業員が安心して受検できる仕組みづくりや、結果を分析したうえで、より快適な職場環境の整備が求められます。
「分析結果を活かして効果的に環境改善したい」「従業員のメンタルヘルス管理にかかる負担を減らしたい」という企業は、ストレスチェックの外部委託やサービス導入を検討するのがおすすめです。ストレスチェックの実施・集団分析を効率化し、健康経営に取り組みましょう。
ストレスチェックサービスの導入に興味がある方は、以下のボタンからおすすめ製品の一括資料請求も可能です。ぜひ活用してください。