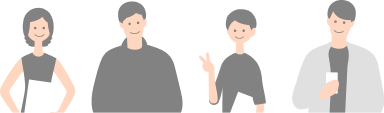マイナンバー管理システムとは?
マイナンバー管理システムは、マイナンバー(個人番号)の取り扱いを支援する製品です。企業のマイナンバー利用が開始されたことで、すべての企業はマイナンバーを適切に管理し、源泉徴収や税金の支払など必要に応じて使用、不要になれば削除・廃棄することが求められるようになりました。人事、給与、財務、会計などのシステムと連携したり、それらの機能を内包している製品もあります。これらの製品を導入することで、安全で適切なマイナンバー管理を実践できます。
検索中…
カテゴリーから探す
マイナンバー管理システム