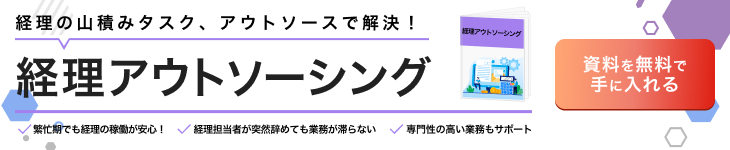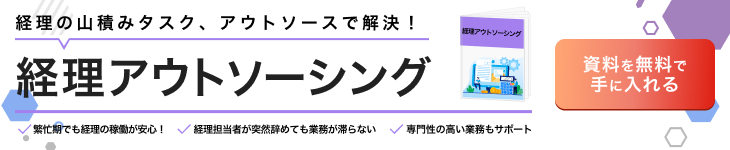
そもそも収益認識基準とは
事業活動により、企業は売上を計上するとともに、費用を計上し、利益を得ることになります。しかし、一定の会計期間がある以上、どのような行為で売上や費用が確定し認識するのか、明確にしなければなりません。ここでは、新収益認識準について解説する前に、どのような認識基準があるのかをわかりやすく解説します。
現金主義
売上であれば現金収入があったとき、費用であれば現金支出があったときに、それぞれ収益・費用を計上する考え方です。
小売店における客商売であれば、売上の発生は現金主義でもよいかもしれません。しかし、企業間では掛け取引が一般化しているため、必ずしても現金の動きと、売上・費用の計上時期は一致しません。
このため、現金主義は会計基準で採用されなくなっています。すべての取引を現金でおこなっている、小規模事業者で採用されている考え方であるといえるでしょう。
発生主義
現金取引には関係なく、取引が発生した時点で収益や費用を計上する考え方です。たとえ掛け取引により、入金や支払いが数か月先であっても、取引が発生した時点で収益や費用を計上します。
ここでいう「発生」とは、経済価値の増減のことをいいます。価値が増加すれば収益が発生し、価値が減少すれば費用が減少したと考えるのです。この考え方にもとづき、減価償却費の会計処理は、発生主義に基づいておこなわれています。
しかし、発生主義は、客観性のない主観により計上することも可能です。このため、発生主義は、費用認識には用いられていますが、収益認識には一般的には用いられていません。
実現主義
収益を、実現の事実に基づいて計上する考え方です。製品やサービスの提供が実際におこなわれ、それを確かに受け取ったという事実にもとづき収益計上がなされます。収益については、主観ではなく客観的事実に基づいて計上されるべきという考え方が反映されたものであるといえるでしょう。
実現主義といっても、「実現」の認識基準は企業によって異なるのが実情です。一般的な販売業の場合、出荷の事実で収益認識する「出荷基準」、納品完了をもって収益認識する「納品基準」、顧客の研修をもって収益認識する「研修基準」など、企業によって「実現」の認識基準は異なります。
費用の認識は発生主義を用い、収益の認識は、より厳密な実現主義を用いることが一般的です。
新収益認識基準とは
昭和24年に制定された企業会計原則では、収益の認識基準について、以下の原則に従うことが定められています。
売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。ただし、長期の未完成請負工事等については、合理的に収益を見積り、これを当期の損益計算に計上することができる。
しかし、前述のように実現主義を採用していたとしても、企業によって認識基準は異なるのが実情でした。一方で、国際的な会計基準では、収益認識基準は明確に定められています。
このため、日本でも収益認識基準が見直され、新しい新基準が定められるようになったのです。新収益認識基準の適用時期は、2021年4月1日以後から開始される事業年度からとなります。
なお、収益認識に関する会計基準の適用指針は随時見直されており、最新版は以下のサイトより確認できます。
参考:収益認識に関する会計基準の適用指針|企業会計基準委員会
制度の概要
新収益認識基準では、いままで不明確であいまいだった認識基準を、「履行義務を充足した時に認識する」と定めました。ここでいう「履行義務」や「充足」といった用語が分かりづらいこともあり、新収益認識基準を細部まで理解することは簡単なことではありません。
まずは、収益の認識は5つのステップを踏むということを理解してください。
- 1.顧客との契約の識別
- 2.契約における履行義務を識別
- 3.取引価格の算定
- 4.履行義務に取引価格を配分
- 5.履行義務の充足による収益の認識
顧客との契約にもとづき、履行義務を明確化することが最初のステップです。明確化した履行義務に従って、取引価格を適切に配分し、収益を認識する流れになります。
例えば5年間の保守費用が含まれるパソコンを販売した場合、パソコンについては収益計上できますが、5年間の保守費用は履行義務を果たしていないため、収益とは認められず売上計上ができません。
適用範囲
新収益認識基準には、特段、適用会社の定めは設けられていません。実質的に、監査の対象になる大会社や、上場企業が対象になると考えてよいでしょう。
中小企業の場合は、「中小企業の会計に関する指針」などが用いられており、新収益認識基準は反映されません。しかし、任意適用は可能なので、将来の株式上場を予定する企業などは、新収益認識基準に基づく会計処理を採用してもよいでしょう。
工事進行基準への影響
ITベンダーによっては、長期間にわたりソフトウェア開発をおこなうため、早期に現金化するために、実現主義にもとづき、出来高に応じて収益認識することがありました。
しかし、新収益認識基準では、これが厳格化され、条件を満たさないと収益認識できません。場合によっては、長期にわたるソフトウェア開発などは、現金化が遅れてしまい資金繰りに窮する可能性もあるのです。
従来の工事進行基準
工事進行基準では、あらかじめ定めた条件をもとに、1年以上の長期にわたるプロジェクトを分割計上し、収益認識を分散化することができました。
一般的には、工事収益総額、工事原価総額、決算日における工事進捗度などを考慮に入れてプロジェクトの進捗度をはかり、これにもとづき収益を按分し売上計上します。
新収益認識基準における工事進行基準
新収益認識準では、工事進行基準も「履行義務を充足した時に認識する」という原則が採用されます。つまり、履行義務が充足されていない工事については、収益計上できなくなるのです。新収益認識準では、工事進行基準が以下のように明確化されることになります。
- 1.企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること
- 2.企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるまたは資産の価値が増加し、当該資産が生じるまたは当該資産の価値が増加するにつれて、顧客が当該資産を支配すること
- 3.次の要件のいずれも満たすこと
・企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること
・企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること
このように、新収益認識基準では、工事進行基準の進捗度の認識が厳密になり、進捗度を合理的に見積もることができる場合にしか収益認識できません。長期にわたるソフトウェア開発などのプロジェクトを分割計上して早期現金化を図るのであれば、顧客との契約時に条件を明確化し、進捗度を合理的に見積もることができるようにしなければならないのです。
原価回収基準
プロジェクトの進捗度を合理的に見積もるといっても、困難な場合もあるかもしれません。そこで、新収益認識基準で定められたのが、原価回収基準です。工事原価の発生基準によって、進捗度を算定することができるのです。
いずれの場合でも、新収益認識基準では、進捗度の算出は明確なルールのもとでおこなわなければなりません。
ITベンダーに影響が大きい新収益認識基準
新収益認識基準が与える影響は、経営者や経理担当者、法務担当者だけではありません。現場の営業が日々提出している見積もりについても、新収益認識基準にもとづいて作成しないと、分割計上ができないかもしれません。
SEやプログラマーについても、今まで以上に細かく工数計算し、プロジェクトの進捗度を算出することもが求められる可能性もあります。特に、長期にわたるプロジェクトを進めることが多いITベンダーに与える影響は決して小さくありません。